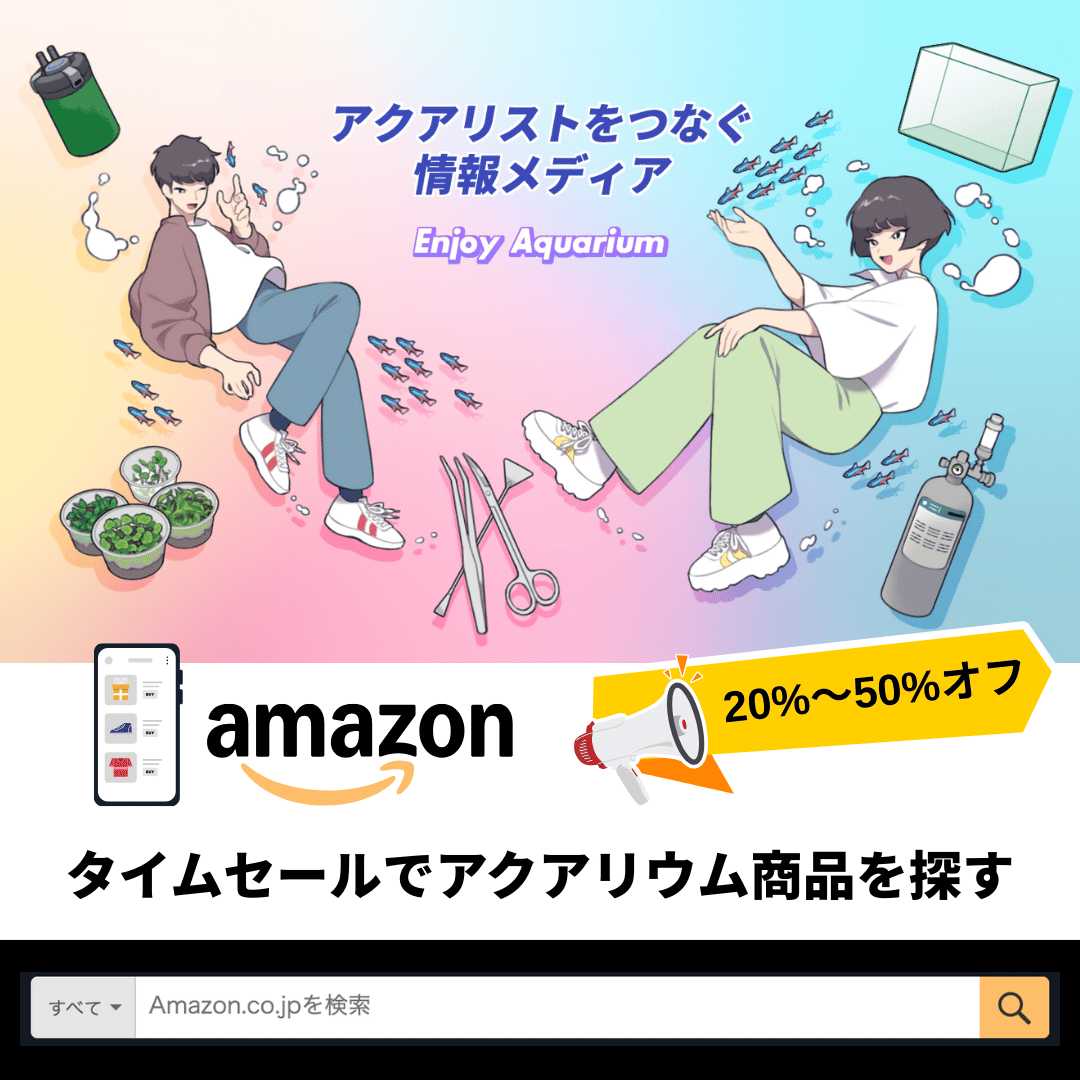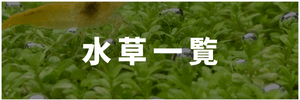
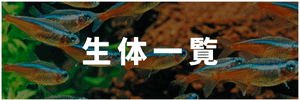




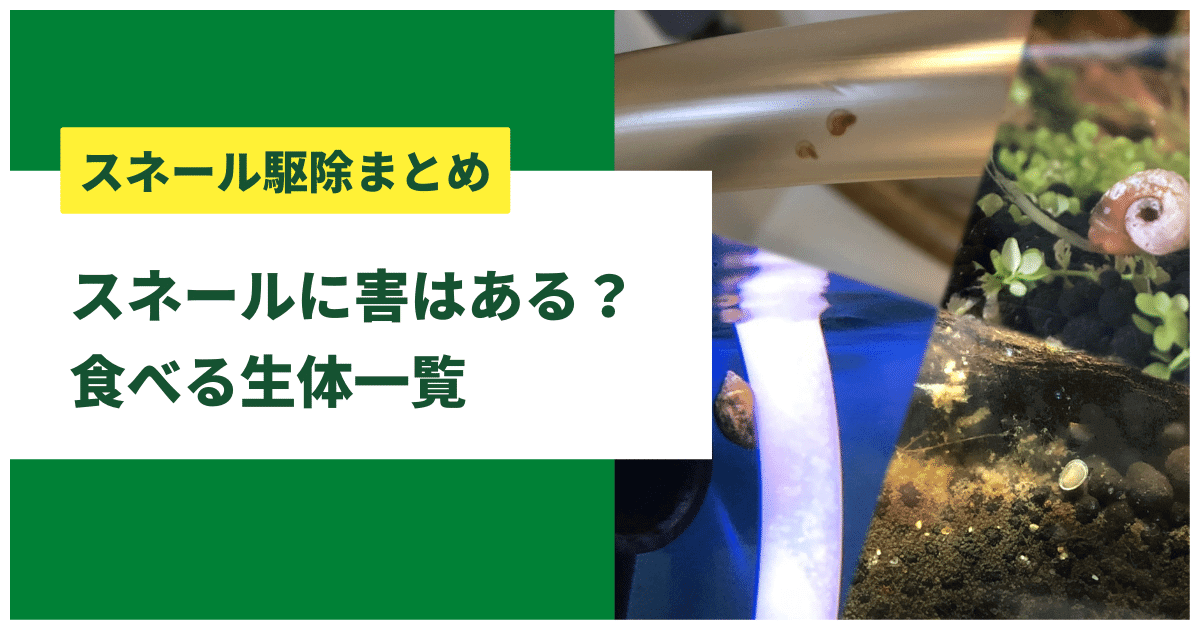

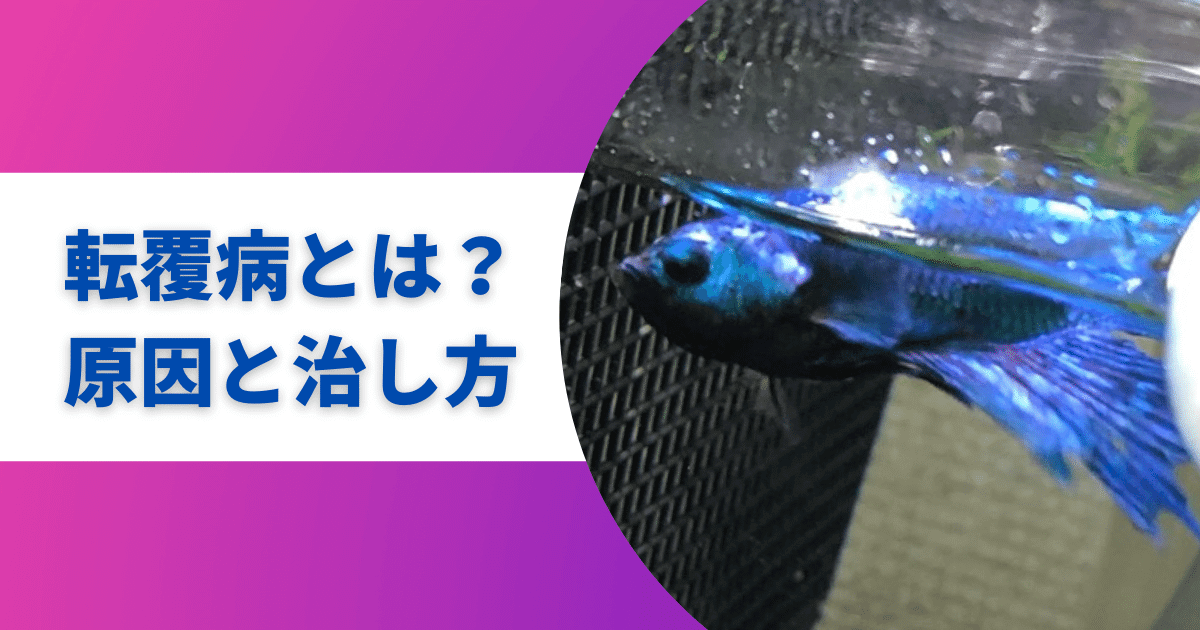
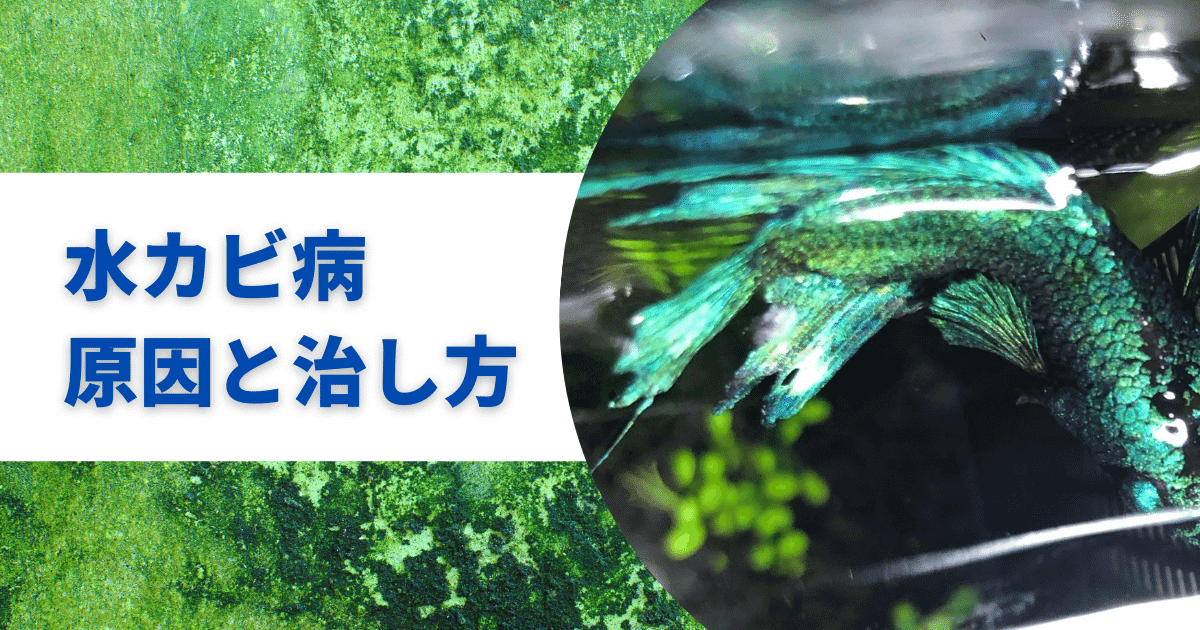




腹水病は抱卵しているのか?と一瞬淡い期待を寄せてしまいがちですが、異様の膨らみからそれが違うことが分かると焦りや戸惑いに変わります。すぐさま死んでしまうことは少ないですが、病状に対して適切な処置を行わないと長生きできないのは事実です。本記事では腹水病の症状や治療法、見分け方などについてまとめているので参考にご覧ください。

腹水病とは魚のお腹が空気が入っているかのようにパンパンに膨れ上がる病気です。歪な形をするよりも滑らかに綺麗に丸々してしまう状態を指します。内臓疾患によって内部に水が貯まることから「腹水病」と言われています。
初期症状の段階は薬浴や給餌のコントロールで改善することもできますが、それでも回復しない場合はそのまま死を待つしかないということにもなりえる難病です。
| 初期症状 | 食欲が低下し、泳ぐ姿が鈍くなる。他の病気に予兆もあり断定は難しい。 |
|---|---|
| 中期症状 | お腹に膨らみが現れるようになる。妊娠しているのか見分けが付きづらいのが特徴。テトラ系は跳ねるような泳ぎ方になりやすく動きづらそうな姿になる。糞が白っぽくなる。 |
| 末期症状 | お腹がパンパンになり、排便もほとんどしなくなってしまう。個体によって食欲があるものもいる。糞が白っぽくなる。 |
初期症状の段階で転覆病や松かさ病などを併発する可能性があるため、いつでも薬浴できる状況を用意しておく必要があります。特に体の大きいベタや金魚は状況把握がしやすいため、異変を感じたら塩浴から行い始めるのも良いでしょう。
腹水病になりやすい品種はベタや金魚、グッピーが特に目立ちます。その他にはネオンテオラやレッドテトラなんかもなりやすいです。餌をドカ食いし、体型がハチェット型やボール型になりやすい魚が発症しやすいのかもしれません。
水質環境が悪い状態だと病気の発症がしやすくなるというのは誰しもが分かることでしょう。ただ、汚れ以外にも魚へのストレスはかかります。例えば、水換えの頻度(量も含む)が逆に多く、水槽内の水を綺麗さっぱりにしていたりしませんか?
特に金魚飼育する上で金魚は水を汚しやすい性質上、景観を綺麗にするために多くの水を一気に取り替えるということをしてしまいがちです。この際の水質変化が多いためにストレスから病気につながってしまうケースも珍しくありません。
適度な水替えは1週間に1回、水の3分の1を入れ替えるといった方法がベターです。自身の水槽環境を考慮しながら徐々にベストなタイミングと量を定めると良いです。

魚の給餌には適切な量と餌やりのタイミングが重要です。過度にあげすぎてしまえば水質汚染に繋がります。他には開封してから月日が経過した古い餌を与えると消化不良を起こしやすくなります。
また、上記に加えて餌やりの時間も気をつけなければなりません。ライトが消灯している時間や消灯間近に餌を与えると消化不良を引き起こしやすいです。魚の消化時間は2時間以上かかる場合もあると言われていますので、消灯の2時間前には夕食を済ませて置くのが理想です。(魚消化時間は種類によって諸説あります。)
腹水病は松かさ病と同じくエロモナス・ハイドロフィラー(Aeromonas hydrophila)によって引き起こされると言われています。エロモナス・ハイドロフィラーは常在菌といってどの水槽内にも潜んでいる菌です。
先述したようにストレスによって免疫低下を引き起こすことでエロモナス菌に感染してしまう可能性があります。エロモナス菌の治療にはグリーンFゴールド顆粒、観パラDなどが挙げられます。
| 6L以上の容器 | 魚を隔離するように必要 100均でも大体入手できる |
| グリーンFゴールド | 根本治療薬 ネットやショップで購入できる |
| 2Lペットボトル | 薬の希釈に役立つ |
| 1ml刻みの計量カップ | 希釈した薬液を入れるのに役立つ シリンジなら100均でも購入可 |
| ただの塩 | 薬を用意するまでの繋ぎや併用として |
| ヒーター | 冬場は治療用に1台必要 |
| クーラー/ファン | 夏場は水温上昇が致命的なので必須 |
| エアーレーション | 酸素と少しの波を立てることに |
隔離水槽(容器)の中の水を0.5%程度の塩分濃度にしたいところ。1000mlに対して5gの塩を入れることで0.5%に近い塩分濃度にできるので隔離水槽の水量をしっかり確認した上で塩を入れて溶かしていきましょう。(あらかじめ用意した2Lペットボトルでおおよその水量を把握しておくのがベスト)
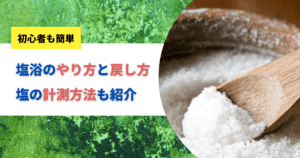
塩でエロモナス菌を殺すことはできず、根本的な治療をすることはできません。しかし、塩浴を行うことで浸透負荷がなくなり、魚自身の治癒能力を上げることが狙えます。
人間も自己回復力が上がれば病気が回復のと一緒です。まずは1週間ほど塩浴をしつつ、餌を与えずに様子を見ます。体内の糞や水を排出できれば徐々に膨らみは緩和し健康状態に戻ることができます。
| グリーンFゴールド2g(1袋) | 1gあたり40L(2Lペットで80L分) |
2LペットボトルにグリーンFゴールド顆粒を入れます。その後、カルキ抜きをした水を入れて蓋をし、よく振って混ぜます。そうすることで濃度の高い薬液を作ることができます。この薬液をそのまま容器に入れてはいけません!
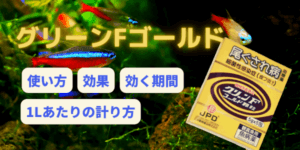
1Lあたりの薬液の投入量が決まっているので自身の隔離水槽の水量に合わせて入れましょう。10L以下の場合は計量カップやシリンジで的確に計って入れないと濃すぎる状態になってしまいます。残った薬液は光に当たらないようアルミホイルなどで包み、冷蔵庫に保管しておきましょう。保管する理由は後述します。
| 飼育水量 | 投入適量 |
|---|---|
| 1L | 25ml |
| 2L | 50ml |
| 3L | 75ml |
| 4L | 100ml |
| 5L | 125ml |
| 10L | 250ml |
| 20L | 500ml |
| 30L | 750ml |
| 40L | 1L |

グリーンFゴールド顆粒の薬効は5日〜7日なので、薬浴目安を5日間、換水に3日かけるという認識で運用するのが良いでしょう。治癒していない場合は、入れ替えた水の量だけ再度薬を投入し、改めて5日間様子を見ます。先述したストックしてある薬液があるとスムーズに行えます。(冷蔵庫から出した際は温度調節に気をつけてください。)
薬浴中も水の汚れが気になる場合は換水をしましょう。ホースで適当に換水すると再度入れる薬液の量が分からなくなってしまうので1Lや2Lペットボトルを基準に入れ替えを行うとやりやすいし正確でしょう。
薬浴を止めようと決めた日に半分の水を入れ替え(1日目)、翌日にさらに半分の水を入れ替える(2日目)、さらにその翌日に全ての水を入れ替えて正常の飼育水に戻してあげよう。(3日目)
薬餌は等倍に薄めたグリーンFゴールド顆粒(1Lあたり25mlを溶かしたもの)にいつもあげている餌を30分浸し、光が当たらない場所で乾燥させて完成になります。出来上がった餌は小さいジップロックなどで空気を抜いた状態で保管するようにしましょう。


腹水病は水が溜まることによる圧迫なため、凸凹したお腹よりツルツルでパンパンという印象が大きいです。個体や症状によって異なりますが、抱卵している場合はパンパンよりふくよかだったりボコボコしている印象です。

また、後ろから見た姿も糞詰まりのような状態であるのが見ていてわかります。テトラ系の小型魚は餌を食べなかったり跳ねたような動きをしているのが印象的でした。ネオンテトラなどは繁殖自体の難易度が高いこともあるため、抱卵よりも病気を疑った方が良いでしょう。
腹水病の様子を見たときにパンパンな様子から押し出して排出できないものかと考えてしまいがちですが、ヒトの力で押してしまうと内臓を圧迫させそのまま死んでしまったり、大きいダメージを与えて衰弱させてしまう可能性があります。