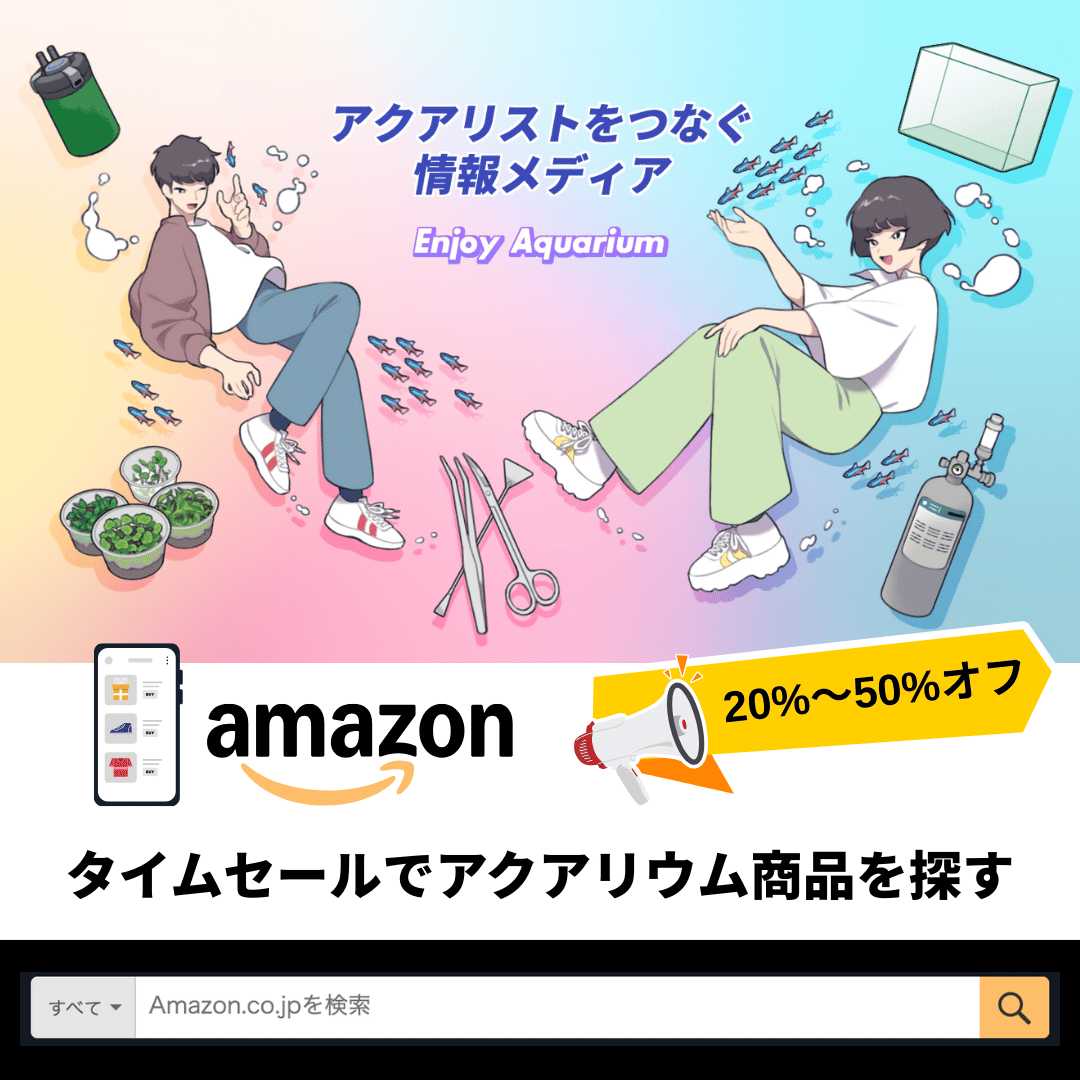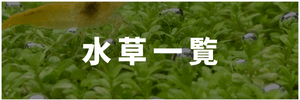
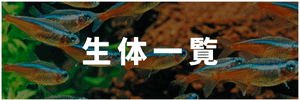




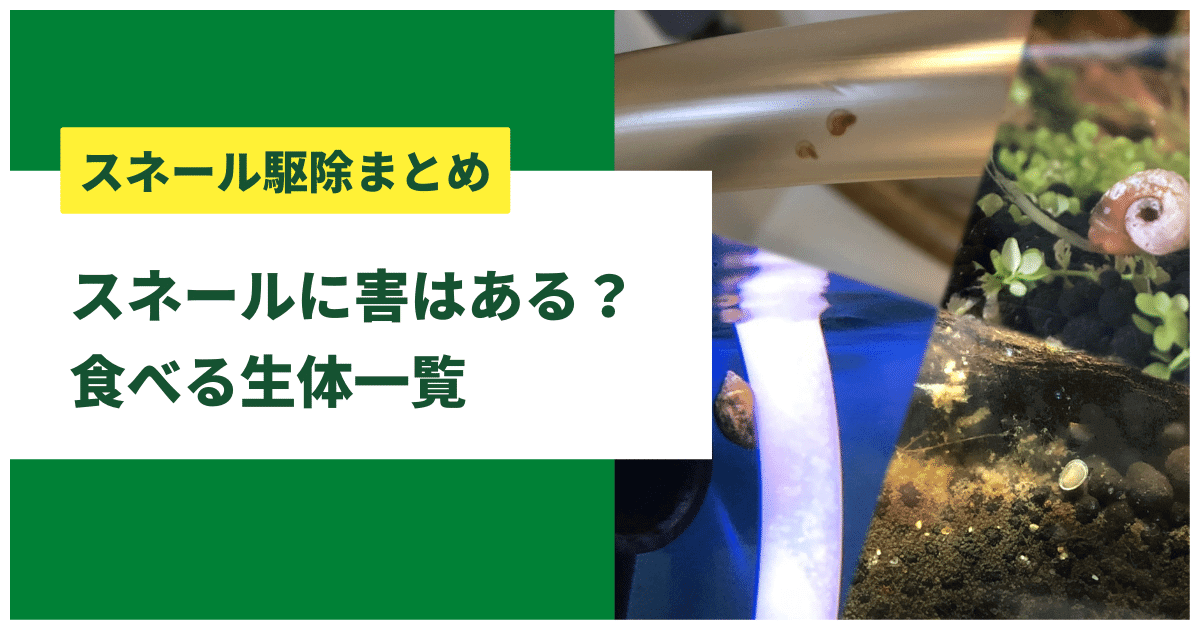

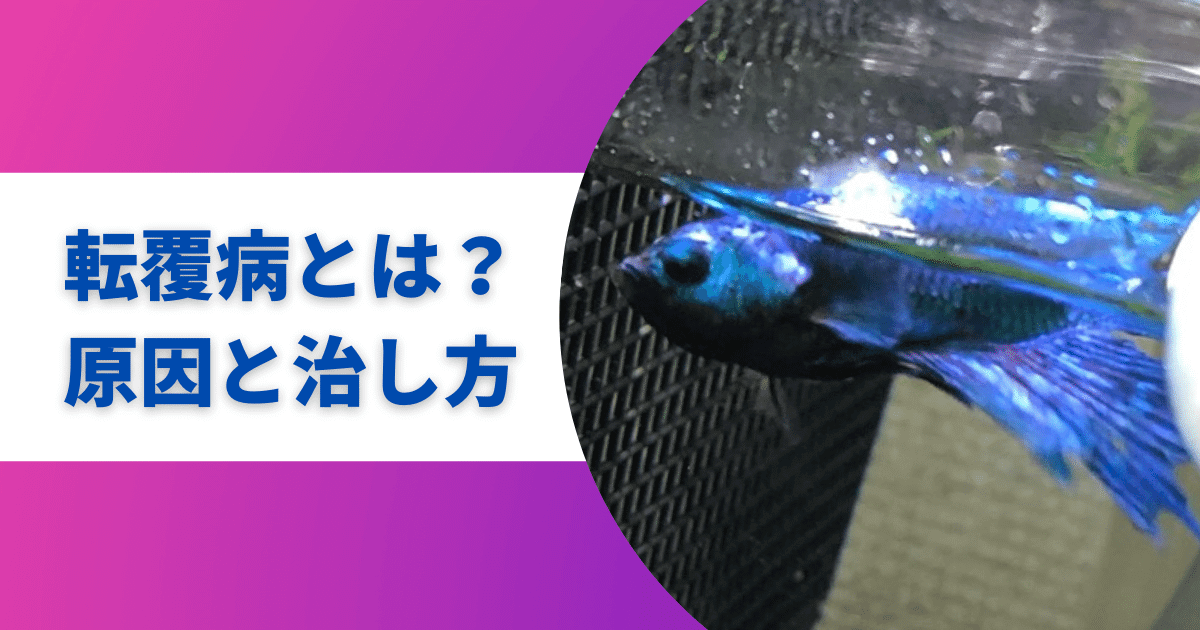
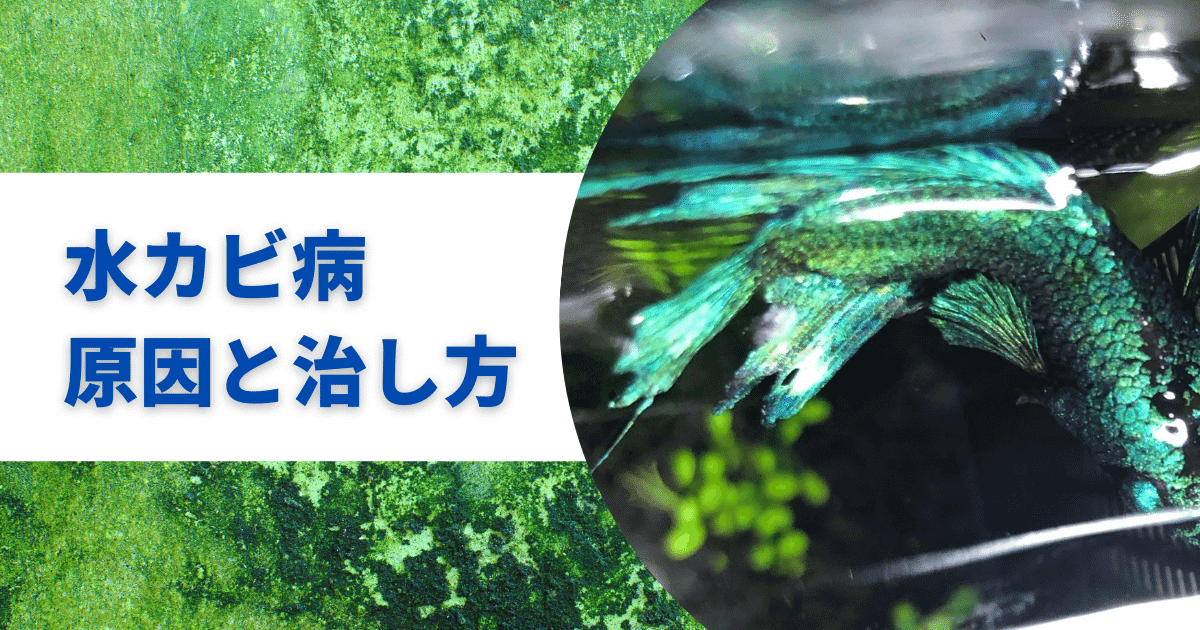



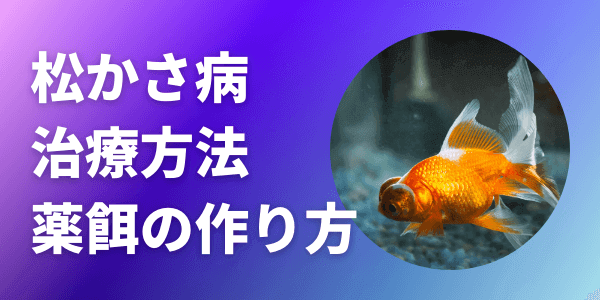
松かさ病は金魚飼育でよく見受けられる病気です。身体が少し膨らんだような状態になり、松かさのように鱗が逆立ってくる症状で知られています。治すことが難しい病気の代表格で一般的な治療方法を行なっても満足に回復できないこともしばしば。本記事では松かさ病とどのように向き合っていくかまとめています。参考にご覧ください。

松かさ病は文字通り魚の表体が「松かさ」のように鱗がめくれ上がる病気。初期症状では治療によって改善が見られますが、水質や魚の体力によっては回復が見込めず命を落としてしまうことが多い難病です。治療難易度としては白点病や尾ぐされ病とは比にならないくらい治療が難しいです。

金魚飼育でよく見られる病気ですが、グッピーやメダカ、ベタ、アロワナといった小さい魚から大きい魚までほとんどがなり得る病気です。
感染していく病気でないため、他の魚にうつることはないとされています。(もちろん人間にもうつりません。)しかし、原因とされるのは後述しますが、エロモナス菌という在中菌によるもの。そのため、水替えをして綺麗な水質を保てなければ他の魚も同じ症状を発生する可能性があります。
| 初期症状 |
|---|
| 鱗が少し浮き出ているように見える |
| 胴体が少し膨らんで見える |
| 泳ぎ方がぎこちない・鈍い |
| 浮いた鱗に小さい白色の粒が見える |
| 鱗の一部が充血して見える |
| 末期症状 |
| 身体が丸々と膨れている |
| 鱗が逆立っている |
松かさ病は丸々と膨れ上がり、鱗も逆立っている状態(誰が見ても松かさ病と分かる)になると末期症状で回復が極めて厳しい状態と認知した方が良いでしょう。また、薬浴などの経験があまりない方や、満足に治療容器の確保ができないといった環境下にある方は対応しきれず助けられない可能性が高いです。
「エロモナス・ハイドロフィラー(Aeromonas hydrophila)」という細菌が原因で発症すると言われています。エロモナスには2種類存在し、「エロモナス・ハイドロフィラー(Aeromonas hydrophila)」は25度〜30度で繁殖すると言われている。主に松かさ病や赤斑病(魚が充血する病)が代表格にあり、総称して運動性エロモナス症と呼ばれることもある。
一方の穴あき病などの原因とされる非定型エロモナス・サルモニシダ(A salmooicida)は低水温で繁殖する。そのため、この両者の認識を誤ると間違った治療法をしてしまうので注意が必要。
参考:月刊錦鯉96年8月号 連載・魚病ノートNo.4(協力)錦彩出版
松かさ病はエロモナスハイドロフィラが原因ではありますが、淡水であればエロモナス菌はどこにでも存在しうるため、お魚の免疫力が高ければ病気は発現しないでしょう。しかし、新しく迎えた時の水質変化によるストレスや、混泳がうまくいかなった時などに生じる外傷が原因で発病してしまうことがあるようです。
水合わせはもちろん、混泳相性にも気をつけ過密飼育を避けるようにしよう。
水換え時に水温が上下が激しい場合にストレスを感じ発病してしまうこともあるようです。上記とほぼ同じ理由に当たりますが、夏冬といった極端な水温変化が起こる季節には特に注意が必要です。
水槽と注ぐ水の温度は同一にしたいところ。
消化不良によりエロモナス菌に感染してしまうケースもあるようです。消化不良は転覆病にもつながる可能性があるため、普段から餌の量や餌やりの時間を考慮する必要があります。
餌のやりすぎや消灯間際の餌やりなどは避けよう。
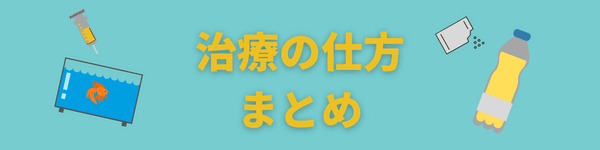
| 6L以上の容器 | 魚を隔離するように必要 100均でも大体入手できる |
| グリーンFゴールド | 根本治療薬 ネットやショップで購入できる |
| 2Lペットボトル | 薬の希釈に役立つ |
| 1ml刻みの計量カップ | 希釈した薬液を入れるのに役立つ シリンジなら100均でも購入可 |
| ただの塩 | 薬を用意するまでの繋ぎや併用として |
| 18~22度設定ヒーター | 冬場は治療用に1台必要 小さい物で大丈夫(大型魚は別) |
| クーラー/ファン | 夏場は水温上昇が致命的なので必須 |
| エアーレーション | 酸素と少しの波を立てることに |
主に金魚飼育下で見られる症状ですが、水温は22度程度までを目安として設定しておきましょう。松かさ病はすぐに治癒できる可能性は低いので隔離容器で治療を行うことをおすすめします。
冬場は熱帯魚向けの固定ヒーターの場合、26度前後であることがほとんどなので不向き。金魚やメダカ向けの18〜22度のヒーターか、サーモスタッド管理できるヒーターを活用しましょう。夏場はクーラーやファンといった冷却グッズを忘れずにつけましょう。
エアレ、ヒーターorクーラー/ファン
隔離水槽(容器)の中の水を0.5%程度の塩分濃度にしたいところ。1000mlに対して5gの塩を入れることで0.5%に近い塩分濃度にできるので隔離水槽の水量をしっかり確認した上で塩を入れて溶かしていきましょう。(あらかじめ用意した2Lペットボトルでおおよその水量を把握しておくのがベスト)
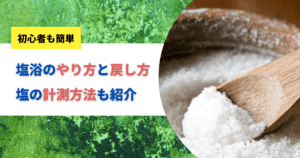
| グリーンFゴールド2g(1袋) | 1gあたり40L(2Lペットで80L分) |
2LペットボトルにグリーンFゴールド顆粒を入れます。その後、カルキ抜きをした水を入れて蓋をし、よく振って混ぜます。そうすることで濃度の高い薬液を作ることができます。この薬液をそのまま容器に入れてはいけません!
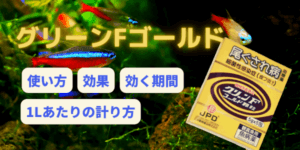
| 飼育水量 | 投入適量 |
|---|---|
| 1L | 25ml |
| 2L | 50ml |
| 3L | 75ml |
| 4L | 100ml |
| 5L | 125ml |
| 10L | 250ml |
| 20L | 500ml |
| 30L | 750ml |
| 40L | 1L |
1Lあたりの薬液の投入量が決まっているので自身の隔離水槽の水量に合わせて入れましょう。10L以下の場合は計量カップやシリンジで的確に計って入れないと濃すぎる状態になってしまいます。残った薬液は光に当たらないようアルミホイルなどで包み、冷蔵庫に保管しておきましょう。保管する理由は後述します。
グリーンFゴールドの薬効は5日〜7日なので、薬浴目安を5日間、換水に3日かけるという認識で運用するのが良いでしょう。治癒していない場合は、入れ替えた水の量だけ再度薬を投入し、改めて5日間様子を見ます。先述したストックしてある薬液があるとスムーズに行えます。(冷蔵庫から出した際は温度調節に気をつけてください。)
薬浴中も水の汚れが気になる場合は換水をしましょう。ホースで適当に換水すると再度入れる薬液の量が分からなくなってしまうので1Lや2Lペットボトルを基準に入れ替えを行うとやりやすいし正確でしょう。
薬浴を止めようと決めた日に半分の水を入れ替え(1日目)、翌日にさらに半分の水を入れ替える(2日目)、さらにその翌日に全ての水を入れ替えて正常の飼育水に戻してあげよう。(3日目)
薬餌は等倍に薄めたグリーンFゴールド顆粒(1Lあたり25mlを溶かしたもの)にいつもあげている餌を30分浸し、光が当たらない場所で乾燥させて完成になります。出来上がった餌は小さいジップロックなどで空気を抜いた状態で保管するようにしましょう。
松かさ病の対策は適度な水替えとよく言われますが、水温合わせを行なってから新しい水を入れるように心がけましょう。夏場は暑くなりすぎた水槽を冷やすために、冷たい水をドボドボ入れたり…全体の水温は下がりますが、魚への負荷は大きいので要注意です。冬場は逆に低温になりすぎたり、温度高めの水を入れちゃったり、ズボラ管理ほど危険なものはありません。魚の病気は確実に治すことが難しいので病気にならないよう日頃の対策が必要ですね。
松かさ病はエロモナス感染症の1つなため、メチレンブルー水溶液で塩浴しても効果ありません。同様にアグテンも効果が見込めません。グリーンFゴールド顆粒やグリーンFゴールドリキッド(初期のエロモナスに有効)、観パラDを使って治療を行いましょう。
エロモナス・ハイドロフィラ(運動性エロモナス)という細菌の感染が原因です。新しく迎えた時の水質変化によるストレスや、混泳がうまくいかなった時などに生じる外傷が原因で発病してしまうことがあります。
松かさ病はエロモナス感染症の1つなため、メチレンブルー水溶液で塩浴しても効果ありません。同様にアグテンも効果が見込めません。グリーンFゴールド顆粒やグリーンFゴールドリキッド(初期のエロモナスに有効)、観パラDを使って治療を行いましょう。